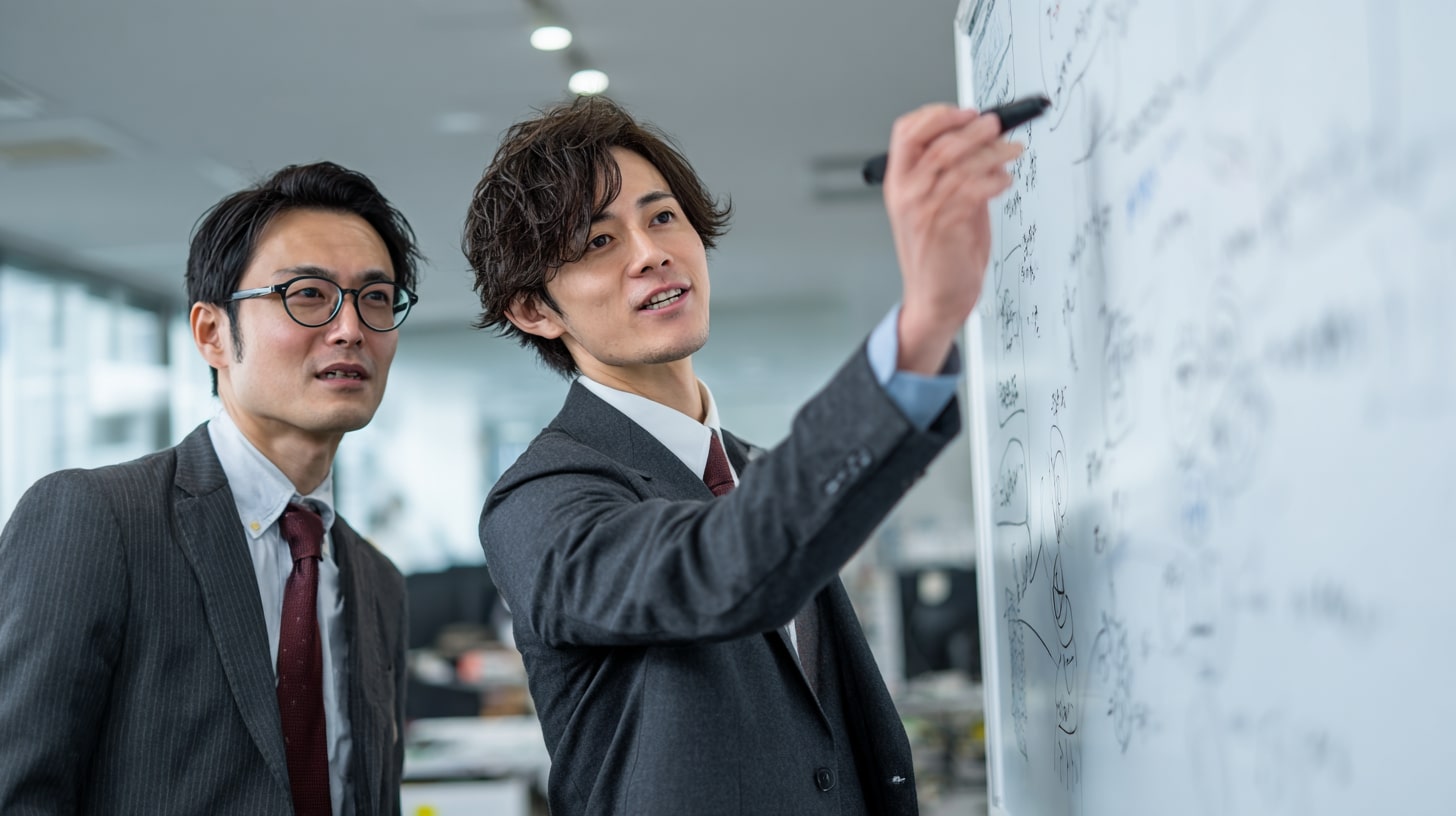ファクタリングメリットの最大の誤解〜借金じゃないのに借金扱いされる理由
私が三井住友銀行で法人融資を担当していた頃、ある中小企業の社長からこんな相談を受けました。
「山岡さん、ファクタリングって使ったら銀行からの印象悪くなりますかね?」
その時は軽く「大丈夫ですよ」と答えたものの、今思えばその社長の懸念は実に的を射ていました。
ファクタリングは確かに借金ではありません。
売掛債権の売買という、至極まっとうな商取引です。
にも関わらず、なぜか「借金扱い」されてしまう。
この現象の裏には、金融業界の古い慣習と、実は我々銀行員の偏見が潜んでいるんです。
「借りない経営」を追求してきた私の視点から、この不可解な現象の正体に迫ってみましょう。
ファクタリングの基本と誤解
ファクタリングの仕組みとは?
まず基本から整理しておきましょう。
ファクタリングとは、事業者の資金調達手法の一つで、売掛金(売掛債権)をファクタリング会社に売却して現金化する金融サービスです。
要するに、将来入ってくる予定のお金を、手数料を払って今すぐ現金に換える仕組み。
古本屋に本を売るのと、本質的には同じです。
違うのは、売るものが「本」か「売掛金という権利」かだけ。
一般的な資金調達との違い
ここで重要なのは、ファクタリングは、売掛債権(売掛金)をファクタリング会社に売却して資金化するものです。これは民法第466条(債権譲渡)に基づいており、売掛金や給与を受け取る権利は「財産権」として自由に譲渡できるとされています。
つまり、法的にも完全に「売買」なんです。
銀行融資のように「借りて返す」関係ではありません。
売ったら終わり。
あとは買い手が回収するだけ。
なのに、なぜ借金扱いされるのか。
「借金とみなされる」原因となる3つの誤解
実は、この誤解には明確な理由があります。
1. 会計処理の複雑さ
ファクタリングを利用すると利用手数料が引かれるので、差引後に振り込まれた金額を普通預金として計上し、手数料部分は「売上債権売却損」という科目で処理します。
この「売却損」という言葉が曲者なんです。
損失が出ているように見えるから、「何か怪しい取引をしている」と思われがち。
2. 手数料の高さ
融資については利息制限法により、利息の上限や遅延損害金の上限が設定されています。しかしながら、ファクタリングについて、手数料などを規制する法律は存在しません。
銀行融資が年利1〜3%なのに対し、ファクタリングは手数料が2〜20%。
この数字だけ見ると「高利貸し」に見えてしまう。
3. 悪質業者の存在
ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されており、金融庁は注意喚起を行っています。
一部の悪徳業者のせいで、ファクタリング全体に怪しいイメージがついてしまった。
なぜ借金扱いされるのか?
会計処理と金融機関の視点
銀行員時代の私が正直に告白しましょう。
決算書を見て「売上債権売却損」という科目があると、つい身構えてしまうんです。
「何で売掛金を売らなきゃいけない状況になったんだろう?」
「資金繰りが相当厳しいのかな?」
こう考えてしまうのが、銀行員の悲しい性。
銀行系ファクタリングでは親会社が銀行になるので、ファクタリングをしている情報が漏れてしまうリスクがあります。ファクタリングを利用している事を知られてしまうと、企業格付けなどにも影響してしまい次の融資も慎重な対応を取られてしまう事もあります。
実際、こういう「格付けへの影響」を気にする銀行員は多い。
信用調査機関が与える影響
ただし、ここで重要な事実があります。
ファクタリングを使って資金調達しても、信用情報には悪影響が及ぶことはありません。その理由は、ファクタリングがお金を借りる方法ではなく、売掛債権の売買で手元のお金を増やす方法だからです。
つまり、客観的な信用情報には一切記録されない。
問題は、銀行員の「主観的な印象」なんです。
社会的イメージと先入観の根深さ
バブル崩壊後、リーマンショック時を通じて、私は数多くの中小企業の資金繰り支援をしてきました。
その中で気づいたのは、「健全な企業ほど、ファクタリングを使いたがらない」という現象。
理由は明確。
「借金してると思われたくない」から。
でも、これは完全に誤解なんです。
ファクタリングの実務と現場のリアル
銀行員時代の現場エピソードから見る実態
ある製造業の社長が、取引先の支払いサイトが突然延長された時のこと。
「山岡さん、つなぎ資金で500万円貸してもらえませんか?」
審査には3週間。
でも、給料日は来週。
「ファクタリングという方法もありますよ」と提案すると、
「それって、ヤクザみたいな商売でしょ?」
当時の私も、正直そんなイメージを持っていました。
でも実際は違った。
その社長、結果的にファクタリングで資金調達。
手数料は3%。
銀行の短期融資の保証料とほぼ同じ。
しかも、信用情報には一切記録されず、その後の融資審査にも全く影響なし。
資金繰りにおけるファクタリングの使い所
「借りない経営」の観点から言えば、ファクタリングは実に理にかなった手法です。
使うべきタイミング:
- 急な資金需要への対応
- 取引先の支払い延期
- 設備投資の前倒し
- 季節変動への対応
使うべきでないタイミング:
- 慢性的な赤字の穴埋め
- 返済資金の調達
- 投機的な投資
要は「一時的なタイミングのズレ」を解消する道具として使うのが正解。
誤解が中小企業にもたらすデメリット
この誤解のせいで、多くの中小企業が機会損失を被っています。
例えば:
- 大口受注があっても、資金不足で受けられない
- 支払いサイトの長い優良企業との取引を避ける
- 設備投資のタイミングを逃す
実にもったいない話です。
「信用」とは何か?ファクタリングから見える本質
「借りない経営」と信用創造の再定義
50代で銀行を早期退職し、金融アドバイザーとして独立してから、私の「信用」に対する考え方は大きく変わりました。
従来の信用観:
「借金をしない = 信用度が高い」
「現金商売 = 健全経営」
でも、これって本当でしょうか?
実際のビジネスでは:
- 売掛金という「信用取引」が当たり前
- キャッシュフローのタイミング調整が重要
- 資金効率の最適化が競争力を左右
つまり、「借りない」ことと「賢く資金を回す」ことは、全く別の話なんです。
キャッシュフロー重視の企業体質とは
ファクタリングを正しく理解している経営者は、こう考えます:
「売掛金は確かに資産だが、現金になるまでは『絵に描いた餅』」
「手数料を払ってでも、今すぐ現金にする価値がある場面がある」
ファクタリングを利用すれば、売掛金をすぐに現金化できるため、資金調達の速度が大幅に向上します。特にオンラインプラットフォームを利用すれば、通常、最短即日から1週間程度で資金を手にすることが可能です。
これは、現金の「時間価値」を理解した判断です。
哲学的に考える「信用」と経営の関係
年を重ねるにつれ、私は「信用とは何か」をより深く考えるようになりました。
真の信用とは:
- 透明性 – 何をしているかを隠さない
- 継続性 – 約束を守り続ける
- 合理性 – 筋の通った判断をする
ファクタリングを「借金だから使わない」というのは、実は合理性に欠ける判断かもしれません。
適切な場面で適切な手法を選ぶ。
これこそが、真の経営判断ではないでしょうか。
誤解を超えて活かすファクタリング
上手に使えば武器になる資金調達法
私が今、中小企業の経営者にアドバイスするとしたら、こう言います:
「ファクタリングは、使い方次第で強力な武器になる」
具体的な活用シーン:
- 新規取引先との契約
支払いサイトが長くても、ファクタリングがあれば安心して取引開始 - 季節商材の仕入れ
売上の入金前に、次のシーズンの仕入れ資金を確保 - 設備投資の前倒し
競合より早く設備導入して、競争優位性を確保
信用を守りながらファクタリングを使うコツ
コツ1:透明性の確保
- 顧問税理士にも情報共有
- 銀行担当者への事前説明(必要に応じて)
- 社内での適切な会計処理
コツ2:計画的な利用
- 単発利用を基本とする
- 慢性的な資金不足の解決策にしない
- ROI(投資対効果)を明確にする
コツ3:業者選びの慎重さ
- 金融庁の注意喚起を参考にする
- 複数業者での相見積もり
- 契約条件の詳細確認
経営者が知るべき「資金調達の地図」
最後に、「借りない経営」を目指す経営者に向けて、資金調達手法の全体像をお示しします。
即効性重視
- ファクタリング(数日)
- ビジネスローン(1週間)
コスト重視
- 銀行融資(1ヶ月〜)
- 公的融資(2ヶ月〜)
リスク分散
- 複数手法の組み合わせ
- 与信枠の事前確保
ファクタリングは、この地図の中で「緊急時の頼れる手法」として位置づけるのが適切です。
まとめ
ファクタリングへの誤解とその正体
振り返ってみれば、ファクタリングが「借金扱い」される理由は明確でした。
- 会計処理の複雑さによる見た目の悪さ
- 金融機関の古い体質による先入観
- 悪質業者の存在によるイメージ悪化
でも、これらは全て「本質」とは関係のない話。
ファクタリングの本質は、「請求書(お金を受け取れる権利)を売却し、支払いを待たず現金化する」という資金調達モデルなので、借金になりません。
「借りない経営」のリアリズムと展望
「借りない経営」とは、決して「資金調達をしない経営」ではありません。
むしろ、借金に頼らずとも、事業に必要な資金を適切に確保できる経営です。
その選択肢の一つとして、ファクタリングは十分に価値がある。
ただし、使い方を間違えてはいけません。
あくまで「つなぎ」として。
緊急避難的な手段として。
信用とキャッシュフローに向き合う経営者へ
関西弁で言わせてもらうと、「こう見えて、実は現金主義なんですわ」。
でも、現金主義だからこそ、ファクタリングの価値がわかる。
将来の現金を、今の現金に変える。
これは立派な現金主義の実践です。
大切なのは、誤解や偏見に惑わされず、自分の頭で考えること。
ファクタリングが借金でないのなら、借金として恐れる必要はない。
足腰を鍛えるように、経営の基礎体力も鍛える。
その一環として、適切な資金調達手法を身につける。
これこそが、これからの時代を生き抜く「借りない経営」の真髄ではないでしょうか。